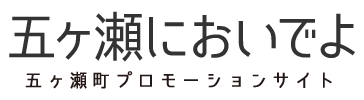伝統・文化
更新日:2023年12月13日
伝統芸能
五ヶ瀬町には宮崎県初となるユネスコ無形文化遺産「荒踊」をはじめとする、伝統芸能が多くあります。
ここでは、その中でも代表的なものをご紹介いたします。
また、多くの伝統芸能においては、次代へと文化を受け継ぐ後継者の不足に悩んでいます。
五ヶ瀬町に移住される皆様が、その担い手となってくださることを切に期待いたします。
荒踊(ユネスコ無形文化遺産、国指定重要無形民俗文化財)

勇壮な「猿」の踊り
今から400年前の天正年間、坂本炎王山専光寺17代の開基坂本城主坂本伊賀守正行がはじめたと伝えられ、その孫坂本山城坂本山城守正次入道休覚が慶長年間になって、その守護神二上大明神(現三ヶ所神社)に奉納する例を定めたと言われています。
行列隊形で踊られる勇壮活発な踊りと、円陣隊形の優雅で静かな踊りを組み合わせた構成で、往時の舞踊を今に伝える伝統を誇る芸能です。
毎年9月下旬に三ヶ所神社、中登神社、坂本城址(荒踊の館)で奉納されます。
臼太鼓踊り

京を追われ、流浪の逃避を続けた平家一族が、秘境椎葉の山里に至る途中、鞍岡の里で華やかな京の都を偲びつつ踊ったのが始まりであると伝えられています。
優雅さの中に凛とした立ち振る舞いを見せる踊には、都の人々の心が偲ばれます。
毎年、祇園神社の秋の例祭にて奉納されます。
棒術

大車流棒術奉納時の様子
町内に伝承されている棒術は、大車流と戸田流の二つの流れがあります。
それぞれ伝授書があり、今では鎮守する神社の神賑行事として、大車流は祇園神社に、戸田流は古戸野神社に奉納されます。
団七踊り
延亨4年(1747)磐城平から延岡藩主に移封された内藤政樹の家中によって伝わり、この地方に伝承したといわれています。桑野内(二ヶ所)と廻渕の3か所に踊り継がれています。
神楽(三ヶ所、室野、桑野内、古戸野、祇園)

五ヶ瀬町では、三ヶ所、桑野内、鞍岡地区に神楽が伝承されています。
その中で三ヶ所・桑野内地区に伝承される神楽は、高千穂神楽で通称岩戸神楽と呼ばれている神楽です。
鞍岡の祇園神楽は、岩戸神楽を軸とし、伊勢・出雲系統のものが含まれていると言われています。
| 神楽名 | 特徴 | 実地日 |
| 祇園神楽 |
「舞開き」の天の岩屋から天照皇大神を手力男命が、手を取ってお迎えする舞は他には見られないといわれています。 |
・7月中旬(鞍岡祇園神社夏季例大祭) ・10月上旬(鞍岡祇園神社秋季例大祭) ・11月中旬(天津神社例大祭) |
| 三ヶ所神社神楽 | 高千穂神楽で通称岩戸神楽と呼ばれている系統です。 | 11月下旬(三ヶ所神社宵神楽) |
| 室野宵神楽 |
今から100年程前に岩戸神楽系統の桑野内神社神楽・古戸野神社神楽から伝わったとされています。 酒漉しの舞いでは農民夫婦の愉快な舞いがあります。 |
12月上旬(室野宵神楽) |
| 桑野内神社神楽 |
使われる面が般若面で、ほかの神楽より多く使用されます。 また、少しテンポが速いのが特徴です。 |
1月上旬(桑野内神社夜神楽) |
| 古戸野神社神楽 |
五ヶ瀬町内では、地元神楽宿で夜神楽が行われるのは古戸野神社神楽だけで、テンポが遅いのが特徴です。 |
1月上旬(古戸野神社夜神楽) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画課 企画政策係
電話番号:0982-82-1717
ファックス番号:0982-82-1720
メールフォームによるお問い合わせ